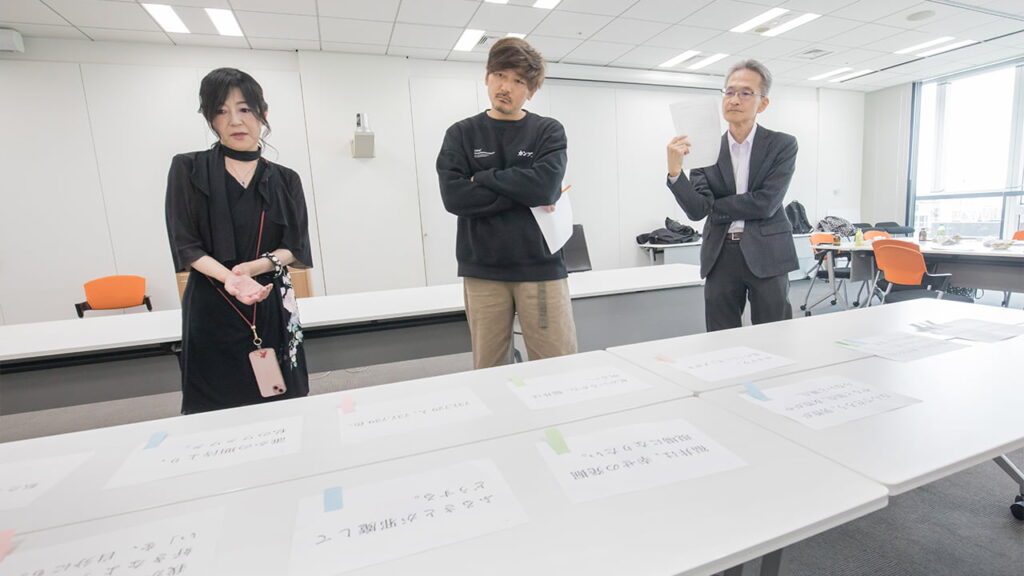マーケティングリサーチ大手のマクロミルは、企業のブランディング活動全体を定期的にモニタリングする「ブランドトラッキング調査」と、個別の広告キャンペーンの効果を測定する「ブランドリフト調査」を組み合わせることで、ブランディング投資の評価を行い、ROIの最大化を支援している。調査データは、ブランド施策を前進させるための「道しるべ」になる——そう語るマクロミルの宮本淳氏と安野将央氏に、調査結果の活用法について聞いた。
広告効果を測定するマクロとミクロの2つ調査
130万人の自社パネルに加え、提携パネルも合わせ国内最大級の約3600万人のネットワークを保有し、消費者調査を通じて企業のマーケティング課題の解決を支援しているマクロミル。注力領域のひとつに、企業のブランディング施策を支援する調査がある。広告をはじめとするブランディング活動の評価を消費者の認識をもとに行うもので、マーケティング投資が適切に行われているかの判断に役立つ。
執行役員デジタルマーケティング本部長の宮本淳氏は「マーケティング予算の多くを占めるのが広告宣伝費です。だからこそ、掛けた投資に対する効果検証とPDCAによる改善が企業にとって重要な命題といえます。我々のような調査会社は、中立な立場で評価・支援しています」と語る。
マクロミル 執行役員デジタルマーケティング本部長 宮本淳 氏
同社が提供する「ブランドトラッキング調査」と「ブランドリフト調査」は、企業のブランディング活動における課題設定から施策効果の定量評価までを一貫してサポートし、ROI改善やブランド戦略のインサイト把握に貢献するものだ。これら2つの調査は、それぞれ異なる目的と役割を担っている。
「ブランドトラッキング調査」と「ブランドリフト調査」
まず「ブランドトラッキング調査」とは、健康診断のように、企業活動全体がブランドに与える影響を定期的に把握するための調査だ。
「例えば飲料メーカーであれば、自動販売機の補充を行うトラックの運転マナーもブランドイメージに影響します。つまり、広告宣伝だけでなく企業のあらゆる活動がブランディングに関わってくる。これを定期的に計測し、ブランドの認知やイメージの変化を追っていくのがブランドトラッキング調査です」(宮本氏)。
一方の「ブランドリフト調査」は、個別のマーケティング施策がブランドにどう作用したかを測定する。
デジタルマーケティング本部の安野将央氏は、「ブランドトラッキング調査が市場全体におけるブランドの状況をマクロ視点で捉えるのに対し、ブランドリフト調査は個別施策が消費者の態度変容にどう影響したかをミクロ視点で評価します。この2つの視点を行き来しながら評価することが重要です」と指摘する。
マクロミル デジタルマーケティング本部 安野将央 氏
ブランドトラッキング調査は多くの企業で実施されているものの、その結果を施策に活かしきれていないケースは少なくない。ブランドリフト調査も、広告会社やメディアが提供するレポートに依存し、広告主自身が主体的に評価できていないこともある。
「広告主の中には『広告会社やメディアからは、良い結果だけを報告されているのではないか』という懸念を持つ方もいらっしゃいます。本来、広告主は自らの広告宣伝活動を客観的に評価すべきです。第三者機関に評価を依頼し、データに基づいて意思決定を行うことが、今後はますます重要になってくると考えています」(宮本氏)。
さらに、ブランドリフト調査は短期的な効果測定に留まりがちだが、広告効果はキャリーオーバー効果などにより中長期的に持続する側面も持つ。ブランディング活動の効果は販促活動とは異なり、消費者の記憶に蓄積され、リピート購買という形で中長期的に現れる。つまり、短期的な効果だけで判断してしまうと、ブランディング広告投資の真の事業貢献を見誤ることになってしまうということだ。
「ブランディング広告への投資は、短期的なROIだけでなく記憶の形成とリピート購買への影響も考慮して評価する必要があります。例えば、ブランドの想起率が1%向上することで、1年後にどれだけの売上増が見込めるのか。この点を考えずに評価すると、短期的にROIがマイナスに見えてしまうこともあり、『これで良かったのか?』と迷いが生じたり、『販促の方がいいのでは』と施策が偏っていってしまう。
マクロミルでは、消費者の購買履歴データや、アンケート調査で取得した消費者の購買行動を組み合わせることで、ブランドリフトによる態度変容効果が、1年後、2年後、3年後と、どのように購買行動に影響するかを予測できます。この中長期的な広告効果の可視化を通じて、広告宣伝に携わる方々の真の貢献度合いを明らかにしていきたいと考えています」(安野氏)。
ブランディング広告への投資効果は中長期で評価することが重要
ブランド想起と購買行動の強い相関
では、具体的にブランディングはどのように購買行動に影響を与えているのだろうか。マクロミルは、自社の消費者購買パネルデータを用いて、ブランド想起のレベルと購買行動の関連性を実証している。
安野氏によると、「消費者のブランド想起にはレベルがあり、いわゆる『助成想起』(ブランド名や写真などを提示して認知を問う)の状態では、あまり購買に影響しないことが明らかになってきている」という。一方で、手がかりなしにブランドを想起できる『純粋想起』や、想起した上で購入候補となる『考慮集合(エボークトセット)』まで、ブランド想起のレベルが上がるほど、購入率やリピート購買は非常に高まる傾向が見られる。
この「想起」を高めるためには、消費者のブランドに対する「イメージの総量」と「利用シーンの連想数」を増やすことが鍵となる。特定のブランドイメージが強化されたり、多様な利用シーンが連想されたりすることで、カテゴリー内での純粋想起が高まり、結果として購買につながるというメカニズムだ。マクロミルでは、これらの知見をブランドトラッキング調査やブランドリフト調査の設計・分析に活かしている。
「定義」と「物差し」の明確化と共有が成功の鍵
マクロミルの強みは、単なる調査結果の提供に留まらず、クライアントの課題解決に向けた伴走支援にある。「お客様の目的やゴールを明確にし、適切なKPIを設定するところから、年間を通じて伴走し、ブランド価値向上を可視化していくことが私たちの役割です」と宮本氏。
そもそも、効果的なブランディング施策のためには、まず「自社にとってブランディングとは何か」「何を達成したいのか」という定義を明確にし、それに基づいた適切なKPIを設定することが不可欠だ。しかし、多くの企業ではこの定義が曖昧なまま、感覚的に施策が実行されているケースが少なくないという。マクロミルでは、クライアントの課題に応じて、このKPI設定の段階から伴走支援を行っている。
ブランディング施策を成果(購買行動)につなげるために、どの「ドライバー」を上げるべきか。KPI設定から伴走支援する
「『自社にとってブランディングのゴール(目的)とは何か』という定義と、それを測る『物差し』を全社で共有することが最も重要です。この物差しは、分かりやすくて誰もが理解し使えるシンプルなものであることが理想的。共通の物差しがなければ施策の良し悪しも判断できないので、社内浸透を図る上で欠かせない第一歩だと考えています」(宮本氏)
安野氏は、ブランディング投資の効果を証明するうえでも、消費者理解が不可欠だと強調する。
「消費者はブランドを相対的かつ主観的に評価するため、自社だけでなく競合ブランドも含めてトラッキングし、相対的な立ち位置を把握することが重要です。そして消費者行動を深く理解し、適切な手法で投資対効果を判断することが、ブランディング投資の成功につながります。ただし、評価基準となる『物差し』が誤っていれば、投資の効果は過小にも過大にも評価されてしまう。私たちは、認知科学、計量経済学、行動経済学などの学術知見に加え、マーケティングサイエンスの知見を活かし、皆様のブランド成長を支援していきたいと考えています」(安野氏)
お問い合せ
株式会社マクロミル